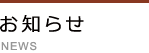当館学芸員によるコラム連載について
2026年01月23日
★★ 連載中 ★★
2015年から読売新聞岩手版紙面にて、当館学芸員が日ごろの博物館活動を紹介するコラム「ミュージアムリポート」を連載中です。諸事情により変更となる場合もございますが、原則として隔週金曜日の掲載となります。ぜひご一読ください。
※複写をご希望の際は、読売新聞お客さまセンター(☎ 03-3246-2323)へお問い合わせください。
【2025年度】
①近藤 良子「アナコンダの皮-収蔵庫に眠るお宝 大集合-」 4月18日
②髙橋 雅雄「ニタリの剥製-巨大な目に小さな口-」 5月2日
③高木 晃「軒平瓦の派遣-歴史解く 重要資料-」 5月9日
④望月 貴史「種市層-化石 地層の観察・記録大切-」 6月6日
⑤工藤 健「国絵図-地図で読み解くメッセージ-」 6月20日
⑥目時 和哉「唐丹村測量之日-岩手に刻まれた忠敬の足跡-」 8月1日
⑦米田 寛「縄文期木製品-用途分からぬ出土資料-」 8月8日
⑧目時 和哉「向鶴紋刀装具-鶴と星 南部氏戦の守り神-」 8月15日
⑨丸山 浩治「学校日誌-戦中戦後 大切な記録-」 8月22日
⑩川向富貴子「せなかあて-先祖いたわる 盆のお土産-」 9月5日
⑪鈴木まほろ「気象観測装置-高山 気候変動の影響探る-」 9月19日
⑫高木 晃「注口土器-縄文人が酒を注いだ?-」 10月3日
⑬戸根 貴之「松尾様-酒造りの守り神 まつる-」 10月17日
⑭渡辺 修二「クマの剥製-クマとの距離 鈴が一役-」 11月14日
⑮古舘 祥子「エアタイトケース-文化財 保存環境整え展示-」 11月21日
⑯大銧地駿佑「手扣帳-目録作成で史実解明-」 12月5日
⑰金子 昭彦「大型土偶の頭部-身長1メートル前後 規格外の謎-」 12月12日
⑱望月 貴史「化石の3D画像-骨格標本にレプリカ重宝-」 1月9日
⑲久保 賢治「河川で発見 餅鉄-粘着力強く軟らかな性質-」 1月23日予定
⑳佐藤修一郎 2月予定
㉑近藤 良子 2月予定
㉒鈴木まほろ 3月予定
㉓渡辺 修二 3月予定
【2024年度】
①工藤 健「岩手のラグビー-旧岩手中で初のプレー-」 4月19日
②近藤 良子「懐かしのおもちゃ-昭和から今 遊びを展示-」 5月3日
③望月 貴史「古生物の想像図-最新の化石研究 図鑑に反映-」 5月17日
④戸根 貴之「かりうち-体験 運と戦略 古代のゲーム-」 6月7日
⑤高木 晃「座る土偶-安産願い『座産』の姿勢か-」 6月21日
⑥丸山 浩治「燻蒸-ガスで殺虫殺菌 代替模索-」 7月5日
⑦米田 寛「旧石器時代の野牛-2万年前の頭骨化石-」 7月19日
⑧佐藤修一郎「合弁の貝化石-棲息域特定 貴重な証拠-」 8月3日
⑨金子 昭彦「ふしぎな縄文-謎解き明かさない展示-」 8月23日
⑩目時 和哉「日常のアーカイブ-角打ち フラスコで堪能-」 9月6日
⑪山崎 遙「虫の防除-薬剤使わず日常で対策-」 9月20日
⑫髙橋 雅雄「猛禽類の献立-生態系の頂点 何食べる?-」 10月4日
⑬渡辺 修二「海洋の捕食者-捕獲に最適 シャチの歯-」 10月26日
⑭髙橋 雅雄「フクロウ類の献立-ネズミや昆虫など捕食-」 11月16日
⑮鈴木まほろ「気候変動-猛暑 高山植物に影響-」 11月22日
⑯川向富貴子「咳に立ち向かう-呪句 病治すおまじない-」 12月6日
⑰大銧地駿佑「御山守-藩有林 村役人が管理・保護-」 12月13日
⑱戸根 貴之「伝統的酒造り-新酒知らせる杉玉看板-」 1月10日
⑲村田 雄哉「詰将棋の歴史-江戸の写本 著名な問題収録」 1月24日
⑳工藤 健「一般からの資料-歴史垣間見る 石垣の申請書-」 2月7日
㉑佐藤修一郎「二戸の貝類化石-熱帯気候の時代示す-」 2月21日
㉒丸山 浩治「学校日誌-事務的な記録 地域史料に-」 3月7日
㉓金子 昭彦「石包丁-弥生期県内で稲作 物証-」 3月14日
【2023年度】
①望月 貴史「標本の成り立ち-殺虫、整理、調査経て登録-」 4月21日
②米田 寛「馬場焼-忘れ去られた幻の陶器-」 5月12日
③金子 昭彦「縄文時代の土偶-出土最多 採集生活関係?-」 5月19日
④渡辺 修二「セミの分布-偏り変化 温暖化影響か-」 6月2日
⑤近藤 良子「北上川-『東鏡』に登場 歴史の舞台-」 6月16日
⑥高木 晃「3500年前の足跡-縄文人を知る足がかり-」 7月8日
⑦戸根 貴之「北上川のダム-水上スポーツに開放も-」 7月25日
⑧髙橋 雅雄「困った鳥 カワウ-放流稚魚食害-」 8月4日
⑨工藤 健「巡幸の石碑-明治天皇の姿を国民に-」 8月19日
⑩村田 雄哉「ノベルティの原点-広告付きの暦 江戸期から-」 9月8日
⑪昆 浩之「縄張り図の欠落-盛岡城図面 意図的に削除?-」 9月22日
⑫鈴木まほろ「シカの食害-早池峰山の植生に影響-」 10月6日
⑬渡辺 修二「キリギリスの仲間2種-似た音程 別々に鳴く-」 10月20日
⑭髙橋 雅雄「夜の生態調査-希少な鳥 自動録音で確認-」 11月10日
⑮目時 和哉「コロナ禍の記憶-感染症の恐怖 資料保存-」 11月17日
⑯丸山 浩治「施設内の照明-LED転換 進まぬ理由-」 12月8日
⑰近藤 良子「蓄音機-温かく臨場感ある音色-」 12月15日
⑱望月 貴史「地層の観察-化石 海岸沿いの崖で-」 1月12日
⑲佐藤修一郎「一戸の珪化木-1700万年前の樹木 化石に-」 1月19日
⑳川向富貴子「日米人形交流-『ミス岩手』答礼の使者-」 2月2日
㉑山崎 遙「劣化防ぐ『荷解場』-寄贈資料『慣らし』館内へ-」 2月19日
㉒村田 雄哉「盛岡藩士最古の棋譜-家元に置き碁で勝利-」 3月8日
㉓米田 寛「旧石器人の携行道具-細石刃 軽量・効率化追求-」 3月22日
【2022年度】
①望月 貴史「岩手の恐竜40年経て-相次ぐ発見-」 4月1日
②金子 昭彦「考古学から見た歴史-平安庶民 竪穴住居に-」 4月15日
③昆 浩之「馬-東北地方に適した役畜-」 4月29日
④丸山 浩治「温湿度管理-カビや虫から資料守る-」 5月20日
⑤工藤 健「干支60年周期-年数を計算-」 6月3日
⑥米田 寛「旧石器時代の装飾品-明日を生きる願い形に-」 6月17日
⑦近藤 良子「不動明王-煩悩立つ 霊鳥の火焔-」 7月2日
⑧佐藤修一郎「化石採集-賢治ゆかりのクルミ-」 7月20日
⑨木戸口俊子「かき氷-かんなで削って 夏の涼-」 8月3日
⑩金子 昭彦「考古学的考え方-事実 愚直に積み重ね-」 8月19日
⑪目時 和哉「吉浜のお盆-高台移転 村長を顕彰-」 9月2日
⑫川向富貴子「弔いのかたち-船の模型 海に流し供養-」 9月16日
⑬髙橋 雅雄「岩手のカエル類-13種生息 違い探して-」 9月30日
⑭渡辺 修二「湿地のバロメーター-クモが教える環境変化-」 10月14日
⑮川向富貴子「菓子の木型-玉櫻堂の道具 継承願う-」 11月18日
⑯鈴木まほろ「湿原の希少種-春子谷地 水流のスゲ-」 10月28日
⑰山崎 遙「酸性紙と脱酸処理-洋紙の劣化 薬品で防ぐ-」 12月2日
⑱工藤 健「境界線の歴史-盛岡の境 明治から変遷-」 12月16日
⑲昆 浩之「家庭の医学-江戸の健康 支えた辞典-」 1月6日
⑳目時 和哉「帝都復興-大震災100年 県人の功績-」 1月20日
㉑村田 雄哉「南天-魔除け 身近な縁起物-」 2月3日
㉒高木 晃「2色の土器-割れた後 強い火で変色-」 2月17日
㉓木戸口俊子「編み笠-雫石あねっこ 手業の装束-」 3月10日
㉔佐藤修一郎「雫石町の成り立ち-大昔は海底 地層に痕跡-」 3月24日
【2021年度】
①望月 貴史「岩手の化石-4億年前の生物も-」 4月2日
②渡辺 修二「過去資料から再発見-クモの調査記録-」 4月16日
③米田 寛「黒曜石-東北の地域間交流示す-」 5月7日
④丸山 浩治「吉田家文書-過去の津波被害記す-」 5月21日
⑤鈴木まほろ「三陸の由来-津波沿岸を印象づける-」 6月4日
⑥近藤 良子「『エビス』-豊漁の神様-」 6月16日
⑦髙橋 雅雄「三陸海岸の海鳥-生物の多様性 展覧会で-」 7月2日
⑧昆 浩之「葛西氏と千葉氏-ゆかりの地 親密さ推察-」 7月16日
⑨渡辺 修二「ワスレナグモ-発見困難『忘れぬよう』-」 7月30日
⑩菅野 誠喜「一関藩と八戸藩-仙台藩・盛岡藩から分割-」 8月6日
⑪山崎 遙「文化財害虫-厄介な存在対策様々-」 8月20日
⑫目時 和哉「閉伊街道と牧庵鞭牛-難所改良に生涯捧ぐ-」 9月3日
⑬望月 貴史「ゴンドワナ大陸-化石示す大地のつながり-」 9月17日
⑭濱田 宏「青虎石製の磨製石斧-丈夫で美しい縄文石器-」 10月8日
⑮川向富貴子「お地蔵様-多様な信仰各地に-」 10月22日
⑯佐藤修一郎「津波観測網-防災へ最先端の備え-」 11月5日
⑰丸山 浩治「弥生後の石器-他地域との交流象徴-」 11月19日
⑱金子 昭彦「教科書と違う歴史-技術や農耕地域で格差-」 12月3日
⑲工藤 健「住所表記-『地割』の起源江戸時代に-」 12月17日
⑳米田 寛「交易品としての琥珀」 1月7日
㉑鈴木まほろ「トラノオ-名に『トラ』がつく植物-」 1月21日
㉒近藤 良子「子守神-安産や子の健康祈る-」 2月4日
㉓髙橋 雅雄「哺乳類の生息調査-多様な野生動物を撮影-」 2月18日
㉔菅野 誠喜「金田一家-政財界で活躍名士輩出-」 3月4日
㉕木戸口俊子「岩手の人形浄瑠璃-藩主に披露し興行権-」 3月18日
【2020年度】
①望月 貴史「太古の海-生命育んだ悠久の時-」 4月4日
②山岸 千人「気温のダイナミズム-地球史に見る自然の神秘-」 4月18日
③渡辺 修二「コイ-侵略的外来種 八幡平に-」 5月2日
④武田麻紀子「鍬ケ崎-南部領随一の繁地-」 5月16日
⑤米田 寛「大漁着-粋な着こなし 港町の祝着-」 5月30日
⑥鈴木まほろ「デジタルアーカイブ-収蔵品 家で見て楽しむ-」 6月6日
⑦丸山 浩治「津波被災資料-塩分除去 紙を水洗い-」 6月20日
⑧小山内 透「製鉄炉-新技術取り入れ進化-」 7月4日
⑨近藤 良子「盛岡竿-竹に漆 実用性兼ね備え-」 7月18日
⑩金子 昭彦「石包丁-胆沢川下流で稲作か-」 8月1日
⑪高橋 雅雄「オジロワシ-風力発電との共存 課題-」 8月15日
⑫望月 貴史「古生態学-化石から太古の動物知る-」 8月29日
⑬昆 浩之「木製のホラ貝-農民の団体交渉にも-」 9月5日
⑭菅野 誠喜「銀行-盛岡の変遷 今に伝える-」 9月19日
⑮目時 和哉「安倍氏-奥六郡で台頭謎多き足跡-」 10月3日
⑯木戸口俊子「人形芝居-淡路発祥の大衆娯楽-」 10月17日
⑰近藤 良子「龕灯-蝋燭 垂直保ち消えぬ工夫-」 10月31日
⑱渡辺 修二「ハッチョウトンボ-消えていく生息地-」 11月7日
⑲昆 浩之「引札-江戸の経済発展で誕生-」 11月21日
⑳菅野 誠喜「川井鶴亭『盛岡城下鳥瞰図』-藩境越え苦難の歴史-」 12月5日
㉑武田麻紀子「大日本帝国憲法-進歩的私案に見る情熱-」 12月19日
㉒山岸 千人「チバニアン-地層に残る地磁気の逆転-」 1月16日
㉓目時 和哉「疫病退散塔-石碑語る感染症の歴史-」 1月30日
㉔米田 寛「炭作り-『鬼滅』で注目の重労働-」 2月6日
㉕金子 昭彦「漆塗櫛-縄文人の高度な技術-」 2月20日
㉖高橋 雅雄「鳥類の剥製-貴重なイヌワシの仮剥製-」 3月6日
㉗濱田 宏「独鈷石-縄文 精神文化の一端-」 3月20日
【2019年度】
①山岸 千人「ドラゴンアイ-氷の瞳 色形、自然任せ-」 4月6日
②武田麻紀子「戊辰戦争-藩士の視点から史実迫る-」 4月20日
③金子 昭彦「弥生の岩手-土器、墓 北海道と交流-」 5月18日
④藤井 忠志「クマゲラ-繁殖地破壊 天敵は人間-」 6月1日
⑤米田 寛「帽子掛けこけし-昭和の増沢塗 希少な作品-」 6月15日
⑥丸山 浩治「火山-噴火の歴史 防災に生かす-」 6月29日
⑦小山内 透「古代製鉄-技術発達、系譜示す遺構-」 8月3日
⑧渡辺 修二「骨-数や形 進化の過程表す-」 8月17日
⑨近藤 良子「蠅とり器-美しく役立つガラス瓶-」 8月31日
⑩山岸 千人「つるし雲(レンズ雲)-岩手山上空 常に形変える-」 9月7日
⑪菅野 誠喜「ふるさとの記憶-陸前高田 文化・歴史の『証人』-」 9月21日
⑫鈴木まほろ「早池峰山-シカ食害 高山植物に危機-」 10月5日
⑬薗田 貴弘「宮古街道-鞭牛和尚の道供養碑巡る-」 10月19日
⑭木戸口俊子「ちゃぶ台-時代を映す家具-」 11月2日
⑮原田 祐参「甲冑-『県民の宝』南部利正の鎧-」 11月16日
⑯渡辺 修二「ヒアリ-殺虫剤 定着助長の恐れも-」 11月30日
⑰近藤 良子「医学書-元禄の民間療法記す-」 12月7日
⑱武田麻紀子「西南戦争の供養絵額-死者の幸せ願い奉納-」 12月21日
⑲濱田 宏「藻塩焼神事-古代の製塩今に伝える-」 1月11日
⑳金子 昭彦「縄文人の装飾-耳飾り 石、土製品が主流-」 2月1日
㉑鈴木まほろ「ヴンダーカンマー-収集の喜び詰まった部屋-」 2月15日
㉒薗田 貴弘「藤田武兵衛と宮古街道-苦難の道路開削事業-」 2月29日
㉓米田 寛「三陸の食-井上円了の舌も魅了-」 3月7日
【2018年度】
①濱田 宏「縄文時代の漁労具-現在に通じる製作技術-」 4月28日
②武田麻紀子「北上川-町の繁栄支える-」 5月19日
③佐々木康裕「三戸南部氏の系図-2種類の相違点を探求-」 6月2日
④小山内 透「羽口-古代の鉄作り支えた管-」 6月16日
⑤渡辺 修二「オナガグモ-細長い姿 獲物はクモ-」 7月7日
⑥丸山 浩治「ゾーニング-文化財守る区画分け-」 7月21日
⑦赤沼 英男「広田湾の海苔養殖-被災した資料を再生-」 8月4日
⑧藤井 忠志「ニホンオオカミ-明治期 急速に姿消す-」 8月18日
⑨原田 祐参「助真-福岡一文字の流れを汲む刀-」 9月1日
⑩鈴木まほろ「ニホンジカ-近年急増 生態系に影響-」 9月15日
⑪米田 寛「カマドのはなし」 9月29日
⑫小山内 透「鞴-炉に送風燃焼効果高める-」 10月6日
⑬近藤 良子「供養碑-祈りにみる動物たち-」 10月20日
⑭佐々木康裕「東鑑-弓馬に優れた近江の義経-」 11月3日
⑮赤沼 英男「実習船かもめ-海を超えた友情の証し-」 11月17日
⑯山岸 千人「災害と地形-自然現象は再び起こる-」 12月1日
⑰藤井 忠志「根付け-ニホンオオカミ痕跡出現-」 12月15日
⑱金子 昭彦「イノシシ-判別困難 縄文期の土製品-」 1月19日
⑲原田 祐参「イノシシと切手-様々な書体の『亥』力強く-」 2月2日
⑳鈴木まほろ「アザミ-県内でも発見 名前に地名-」 2月16日
㉑木戸口俊子「キリガシ-今も残る 70年前の雛菓子-」 3月2日
㉒渡辺 修二「鳥-現代の恐竜示す展示-」 3月16日
㉓薗田 貴弘「宮古街道-難所続き 歴史刻む橋巡る-」 3月30日
【2017年度】
①藤井 忠志「アオバト-鳴き声不気味な魔王鳥-」 4月15日
②小山内 透「たたら-精錬炉跡切り取り展示-」 5月13日
③原田 祐参「巡幸図-明治天皇の滞在地記す-」 5月20日
④佐々木康裕「東鑑-奥羽征伐『武士道』の兆し-」 5月27日
⑤渡辺 修二「クモ相撲-小さな体でがっぷり四つ-」 6月3日
⑥金子 昭彦「遮光器土偶-出土例最多の岩手特産-」 6月10日
⑦丸山 浩治「雨滝論争-土器の変遷巡り議論-」 7月1日
⑧望月 貴史「化石や地層-岩手国内有数の発掘現場-」 7月15日
⑨山岸 千人「ドラゴンアイ-『開眼』の仕組み水位影響-」 7月29日
⑩小野寺俊彦「田山暦-絵で表す暦に潜む『謎』-」 8月5日
⑪鈴木まほろ「外来種-知らぬ間に侵入し定着-」 8月19日
⑫薗田 貴弘「盛岡の橋めぐり-川の街の交通支える-」 8月26日
⑬川向富貴子「学芸員、山へ入る-民俗芸能調査多彩な活動-」 9月2日
⑭赤沼 英男「津波流出の金鉱石-洗浄→脱塩→乾燥で復元-」 9月9日
⑮濱田 宏「鐸形土製品-儀式に使われた垂飾品か-」 9月16日
⑯近藤 良子「大絵馬が語りかけるもの-自由に想像画題楽しむ-」 9月23日
⑰武田麻紀子「代表的岩手人-熱狂生む演説家鈴木舎定-」 9月30日
⑱佐々木康裕「糠部の歴史-中世南部氏の活躍に焦点-」 10月14日
⑲藤井 忠志「サンコウチョウ-子育て雌に主導権-」 10月28日
⑳原田 祐参「金小札茶糸縅二枚胴具足-甲冑が語る南部重信像-」 11月11日
㉑金子 昭彦「亀型土製品-人、動物の特徴が混在-」 11月25日
㉒渡辺 修二「ニホンオオカミ-伝染病や山林開発で絶滅-」 12月9日
㉓小山内 透「考古資料と科学分析-文化史解明の一助担う-」 12月23日
㉔丸山 浩治「被災オルガン-明治期の音色修理で復活-」 1月6日
㉕川向富貴子「サイトギ-祭りの儀礼 氏子に役割-」 1月20日
㉖山岸 千人「火山との関係-噴火記録防災に役立てる-」 2月3日
㉗小野寺俊彦「エジコ-赤ちゃんのけが防止に-」 2月17日
㉘鈴木まほろ「被災押し葉標本-自然の歴史詰まった資料-」 3月3日
㉙赤沼 英男「再生された仏像-修復で制作技法明らかに-」 3月17日
㉚望月 貴史「新種の名付け方-化石発見者学名に-」 3月31日
【2016年度】
①笠原 雅史「製鉄の父-砲術の道突き進む-」 4月2日
②藤井 忠志「クマゲラ-津軽海峡を渡るのか-」 4月23日
③笠原 雅史「大島高任-公平 緻密な意見書-」 5月7日
④原田 祐参「鳥瞰図-色鮮やかな観光案内-」 5月14日
⑤佐々木康裕「秀衡の遺言-奥羽の平和への思い-」 5月21日
⑥渡辺 修二「洞穴生物-地史や分布変遷読み取る-」 5月28日
⑦丸山 浩治「石器-高度な技術破片から採る-」 6月4日
⑧金子 昭彦「腰かける土偶-ポーズが伝える社会情勢-」 6月18日
⑨吉田 充「鉱床-川砂が伝える鉱山の歴史-」 7月2日
⑩望月 貴史「大量絶滅-地層で見る古生代生命史-」 7月16日
⑪小野寺俊彦「田山暦-占い告げる絵がたっぷり-」 7月30日
⑫鈴木まほろ「ハマゴウ-岩手から消えた海辺の花-」 8月6日
⑬齋藤 里香「弓矢-源平合戦に数々の逸話-」 8月13日
⑭川向富貴子「寄贈-花模様 フォルム美しい便器-」 8月20日
⑮赤沼 英男「蕨手刀-日本刀の成立に影響-」 8月27日
⑯小山内 透「製鉄-手間かかる工程解明期待-」 9月3日
⑰近藤 良子「猫の絵馬-飼い主の愛情もにじむ-」 9月17日
⑱原田 祐参「スポーツ-サッカー史に県人の足跡-」 9月24日
⑲藤井 忠志「クマゲラのひみつ-たくさんのアリを捕食-」 11月5日
⑳笠原 雅史「那珂梧楼-松陰と交友『至誠』を説く-」 11月12日
㉑佐々木康裕「加賀美遠光-頼朝一家と親密な関係-」 11月19日
㉒渡辺 修二「イソコモリグモ-大津波で県内から絶滅-」 11月26日
㉓丸山 浩治「黒曜石-古墳時代なめしの道具に-」 12月3日
㉔金子 昭彦「狩猟文土器-粘土で貼り付けた神話-」 12月10日
㉕吉田 充「砂金-水中流れるほど成長-」 12月17日
㉖望月 貴史「カンブリア紀-動物爆発的に多様化-」 1月7日
㉗小野寺俊彦「小正月-豊作願い様々な行事-」 1月14日
㉘鈴木まほろ「マルミノシバナ-湿地埋め立てで避難中-」 1月21日
㉙原田 祐参「参勤交代-大名行列華やかに演出-」 1月28日
㉚川向富貴子「早池峰神楽-国立劇場別世界の舞台-」 2月18日
㉛赤沼 英男「鉄鍋-火所かまどから囲炉裏へ-」 2月25日
㉜小山内 透「たたら製鉄-量産化への設備が進歩-」 3月4日
㉝近藤 良子「茅葺き-補修工事職人の技に注目-」 3月18日
㉞齋藤 里香「鉄道画-一変した日常の風景伝える-」 3月25日
【2015年度】
①藤井 忠志「クマゲラ-幻の鳥ブナの森に追う-」 6月6日
②鈴木まほろ「ブナ-数年に一度たくさんの花-」 6月13日
③渡辺 修二「カワシンジュガイ-子孫育たず進む『高齢化』-」 6月20日
④望月 貴史「ペルム紀の地層-絶滅の跡-」 6月27日
⑤吉田 充「鳴き砂-歴史伝えるミクロの世界-」 7月4日
⑥八木 勝枝「遮光器土偶-高額落札『お宝』化に不安-」 7月18日
⑦羽柴 直人「蓮華形磬-『日爪』の権力示す遺物か-」 8月1日
⑧瀬川 修「資料収集-残したい寄贈者の思い-」 8月8日
⑨佐々木康裕「歴史への招待-文献の背景的確に把握を-」 8月15日
⑩原田 祐参「道中日記-江戸時代の『旅行ガイド』-」 8月22日
⑪笠原 雅史「橋野高炉跡-製鉄携わる人々結集の象徴-」 9月5日
⑫齋藤 里香「鯰尾兜と槍-武将交流カッコよく伝える-」 9月12日
⑬川向富貴子「ドレス-明治の仕立て高校生が制作-」 9月19日
⑭丸山 浩治「火山灰-10世紀の噴火地層に痕跡-」 9月26日
⑮小野寺俊彦「ミノとケラ-わら細工の呼称地域で違い-」 10月3日
⑯金子 昭彦「縄文土偶-立てない人型像お守り?-」 10月10日
⑰赤沼 英男「津波被害-措置措置で修復青い目の人形-」 10月17日
⑱藤井 忠志「クマゲラの巣-快適空間他の鳥獣に人気-」 11月7日
⑲鈴木まほろ「震災後の植物-土中の危惧種が発芽か-」 11月14日
⑳原田 祐参「金沢御山大盛之図-鉱山で働く姿を伝える-」 11月21日
㉑渡辺 修二「意外な発見-公園で珍しい生物-」 11月28日
㉒望月 貴史「生痕化石-動物が生きた証-」 12月5日
㉓佐々木康裕「秀衡と頼朝-『東鑑』が示す政治関係-」 12月12日
㉔丸山 浩治「細石刃-幅数ミリの規格品量産-」 1月9日
㉕八木 勝枝「甲塚古墳の埴輪-被葬者は機織り担う?-」 1月16日
㉖羽柴 直人「仏教文化研究の重要資料-最北の鏡像-」 1月23日
㉗吉田 充「砂金-北上山地の石英脈を調査-」 2月6日
㉘齋藤 里香「日本名山図会-増補で追加二つの岩手山-」 2月13日
㉙瀬川 修「民家-昔の暮らし身近に体験-」 2月20日
㉚金子 昭彦「土偶-年代推定特徴からの比較-」 3月5日
㉛川向富貴子「複製品-学芸員監修の二次資料-」 3月19日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★★ 連載中 ★★
同じく2022年から岩手日報紙面「いわてリレーエッセー 散歩道」に当館学芸員が執筆しています。
①目時 和哉「辺境という希望-『食べる』歴史へのご招待」 2022年3月26日
②目時 和哉「ヒストリー・ブローカー~過去と現在の仲立人というお仕事~」 2022年10月22日
③目時 和哉「ドラえもんの世紀を生きるあなたへ」 2023年6月10日
④髙橋 雅雄「小鳥を探して日本一周」 2024年2月10日
⑤髙橋 雅雄「夏に子育てをするチゴハヤブサ」 2024年8月10日
⑥髙橋 雅雄「追悼 日本一の剥製師」 2025年2月8日
⑦川向富貴子「無用の用」 2025年4月26日
⑧川向富貴子「変容と消失の民俗」 2025年10月25日←New!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆☆ 連載修了 ☆☆
同じく2016年度から2018年度の3年間、朝日新聞岩手版紙面にて当館学芸員によるコラム「県立博物館へようこそ」を連載しておりました。
※複写をご希望の際は、朝日新聞グループビジネスセンターお客様窓口(☎ 03-5540-7094)へお問い合わせください。
【2018年度】
①山岸 千人「岩手の火山-常設展と眺望を体験して-」 4月14日
②金子 昭彦「弥生時代-銅鐸に描かれた階級社会の始まり-」 6月9日
③渡辺 修二「岩手のクモ-体にぐるり 優れた目を配置-」 6月9日
④望月 貴史「モシリュウ-幸運な偶然、恐竜化石の発見-」 7月14日
⑤武田麻紀子「明治14年-岩手の視座から 東北から国を変える意気-」 8月11日
⑥近藤 良子「祈りにみる動物たち-神仏への願い託す存在-」 9月8日
⑦木戸口俊子「オオカミ-身近な害獣が信仰の対象にも-」 10月13日
⑧濱田 宏「塩づくりと流通-平安時代、越後から盛岡に送る-」 11月10日
⑨丸山 浩治「津波かぶった収蔵品-再生の歩み紹介する展示-」 1月19日
⑩米田 寛「古代の『赤』-厄よけ、招福・・・力宿る色-」 2月9日
⑪薗田 貴弘「宮古街道-豪商が作った新道三十里-」 3月9日
【2017年度】
①藤井 忠志「クマゲラ-生息地にツキノワグマも-」 4月14日
②望月 貴史「よみがえる古生物-今の生物を参考に復元-」 5月12日
③金子 昭彦「遮光器土偶の世界-どう使った?観察を元に-」 6月9日
④渡辺 修二「ムジナ-同じく穴にすむけれど-」 7月14日
⑤原田 祐参「刀の鍔-江戸時代に芸術性高く-」 8月11日
⑥佐々木康裕「中世の南部氏と糠部-甲斐ルーツ歴史像に迫る-」 9月8日
⑦小野寺俊彦「雑水釜-台所に流しがないわけは-」 10月13日
⑧小山内 透「中世南部氏と糠部-城主気分で山城登っては-」 11月10日
⑨近藤 良子「ゆく酉くる戌-犬めぐる風習と信仰紹介-」 12月8日
⑩川向富貴子「展覧会『ひとのかたち』-人形に込められた思い-」 1月12日
⑪丸山 浩治「文化財の大敵-極小の虫、侵入防止へ腐心-」 2月9日
⑫赤沼 英男「吉田家文書-被災資料を未来につなぐ-」 3月9日
【2016年度】
①藤井 忠志「クマゲラ-定着にブナ林保護、急務-」 4月8日
②望月 貴史「大量絶滅-第6の危機人間は意識を-」 5月13日
③金子 昭彦「弥生土器-教科書と異なる岩手の歴史-」 6月10日
④渡辺 修二「地域性の危機-生き物外に逃がさないで-」 7月8日
⑤赤沼 英男「被災文化財の修復-複数期間が連携古文書再生-」 8月12日
⑥佐々木康裕「南部氏-糠部への入封時期のなぞ-」 9月9日
⑦川向富貴子「郷土芸能公演-数十年ぶり復活『鹿酒盛』-」 10月14日
⑧小野寺俊彦「氷冷蔵庫-『三種の神器』の登場までは-」 11月11日
⑨鈴木まほろ「砂浜の植物-津波被害受けても回復-」 12月9日
⑩吉田 充「蛇紋岩-砂金が採集できる『県の石』-」 1月13日
⑪丸山 浩治「二戸・舌崎-鉄道開通と縄文遺跡保存-」 2月10日
⑫齋藤 里香「蓑虫山人-明治の岩手描いた放浪画家-」 3月10日
※上記コラムはいずれも著作権など諸権利の問題から、当館において閲覧・複写サービスを行っておりません。